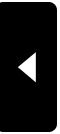2020年07月28日01:52
発声練習考えましょうか≫
カテゴリー │唐津「なんか向上」
脚質バーチャルってなんやねん(あいさつ)
いやどうにもバーチャル・ツール・ド・フランスの楽しみ方がわかんないんすよ。サイクルトレーナーで実際に漕いでるとはいえ「別に本気でやってませんし」「ウチ高地で酸素薄いんで」ってなスタンスのチームや選手も多いから、他人が遊んでるゲーム眺めてるくらいの感じにしかならんのです。
NFLで言うとプレシーズンやプロボウル見てる感じ。やっぱ本気の姿じゃないと楽しめないんだよなー。
ってことで今回は、発声練習本気でやろうぜっていうか。そんな回。
ワークショップで声について扱う場面があると、僕は最初に「発声練習ってやってる?」って聞いてみることが多いです。
まあ、答えはだいたいYesですよ。さすがにワークショップに参加するような人たちですからね、その辺は多少なりともちゃんとしてらっしゃる。
でも「なんのためにやってる?」って聞いてみると、曖昧な答えしか返ってこないことが多いんだなコレが。
ということで、今日は発声練習について考えてみたいと思います。
うん、そうなんだ。
発声そのものについては今週もまとめられなかったんだ。そんな僕に石を投げないでほしい。
声を大にして言わせてもらう。いや、声を大にして言わせてもらうためにちょっと発声練習してから声を大にして言わせてもらう。
稽古時間に余裕がねーんだよ目的持たずにやってるくらいなら他のことに時間使わせてくれよコンチクショーメ。
これは多くの演出家が感じているであろう事実である。
とか偉そうに始めてみましたけど、まーね、わからんでもないんですよ。アマチュア団体なんかの発声練習が非常にヌルい感じになるのはだいたい以下の理由だと思う。
そりゃ惰性でやるだけになりますよ。
もちろん、台詞使った稽古やるときは(演出方針によるけど)日常より多少大きな声や口の動きになるんで、その準備体操的な意味合いでやるってのはわかる。わかるんだけど、だとしたら5〜10分もあれば充分でしょう。そのぶん他のことに時間使いましょうやダンナ。
それから、ウォーミングアップ的な意味合いとしてやっているだけなら、別の疑問が湧いてくる。
発声のバリエーション増やしたり磨いたりするための時間はいつ作るつもりなんすか?
っていう。「私は既にこれ以上の向上が見込めないほど素晴らしい発声ができる」と考えてるなら、ぶっちゃけ役者やめた方がいい。「そうじゃないのはわかってるけど発声練習は無目的」なら、それもやっぱり役者やめた方がいい。どっちにしたって現状認識と問題意識、その改善のための考察と実行っていう、役者として必要とされる最上位クラスのものが欠けてるんじゃねーですか、と。
っつーことで、ちゃんと目的意識を持って発声練習してくださいね。
アマチュア団体なんかでよく見かける風景。
や、発声練習と台詞読みで声質や発声方法が全然違うの、別に全面的に悪いわけじゃないですよ。発声練習をあくまで準備運動と捉えるならね。
でも準備運動だとするなら、せめて終盤はその舞台で使う声で発声練習やった方がいいんじゃないかな、とは思う。
若干話が逸れるんだけど一応触れておくと、アマチュア団体なんかにありがちな「発声練習の声」と「実際に使う声」が違う現象は、「正しい発声方法」に対する誤解に起因してる気がする。
現在の日本で「正しい発声方法」として説明・紹介されるものは、基本的にオペラやミュージカル、ゴスペルなんかの歌唱用の発声方法がベースになってることが多い。ここに至る歴史的・技術的経緯云々をやりだすと読む方も書く方もメンドクサイのでやめるけど(おぃ)、基本は歌うための発声だからね、ナチュラルな喋りにはなりにくいっていうか、あの声で喋ると「しーんぱーいナイさぁぁぁ」な感じになっちゃうワケ。
だから「発声練習は正しい発声方法で」「でも台詞読みは別」って感じになって、ぶっちゃけ時間かける意味の薄いものになっちゃう。
ボイトレなんかも、先生の経歴によるけど基本は歌用。特に最近はマイク使用を前提としたボイトレも多いんで、そうなってくると生声前提な芝居の現場でダイレクトに使えるものではなかったりする。あと近年じゃ声優用ってのもあるか。声優と舞台の発声方法も全然違うよね。
あ、誤解されそうなので言っておくと、これらの発声方法が間違ってるとか、役に立たないってことではないですよ。
って感じ。
じゃあ現代の日本における演劇用の正しい発声方法ってなんなのかって言うと、「なんでもいい」。
いやもちろん、「千秋楽の最後の幕が下りるまで保つ(もつ)声であること」とか、「演出上求められる声量でコントロールできること」とか、ある程度の条件はあるけどね。それがどんな条件かってのは演出次第。その条件さえクリアしてればどんな発声方法でもいいんですよ。
実はこれ、発音や発語についても似たようなことが言えて、その辺の指導ってナレーションやアナウンサーのものが基本になってる(しかもラジオ時代に発展したものが中心。加えて言うなら声優系も役者は見えない前提の喋り)。
いずれにしても、正しいやり方のひとつではあっても、全てじゃない。
だから「正しい発声方法はこれ」って考えて「正しい発声方法で発声練習」とか考えなくていいです。
むしろ発声練習では、自分の声の持つ可能性を追求しましょう。
発声練習の目的やそれによって得られるものってのはひとつではないです。別にいろんな目的があっていいし、それに応じたやり方をすればいい。
まあ、トレーニングってなんでもそういうものでしょ。
1:ウォーミングアップ
否定してたワケじゃねーですよ、と。日常生活から舞台用の幅のある声にいきなり変えるのはなかなか難しいんで、ウォーミングアップを目的とした発声練習は別にアリ。基本そんなに時間かからないので手早く済ませる方法を何パターンかもっておくといいです。
2:役柄の声に慣れる
現在取り組んでいる役柄があって、その声質の方向性が決まっているなら、ある程度その声使って発声練習やった方がいいです。全てをそれでやる必要はないけど、その声質でのコントロール性を上げるなら発声練習が一番いい。というか、この練習を台詞合わせ中にやられても、ぶっちゃけ周りの役者の迷惑にしかならない。
3:新たな声質の開発
芝居はどんな声でもいいってことは、自分の「使える声」を色々持っている方が役者としては有利。これ専用の時間をくれる劇団なんてほとんどないから、発声練習の中で色々試した方がいい。うちの役者はそれなりに舞台経験あるけど、未だに声の開発し続けてる。ありがたい話だ。
4:苦手な部分の克服
ちょっと言い方的に広いんだけど。例えば早口言葉。これ、早く言える言い方でやっても得られるものは多くないんですよ。あえて言いにくい声質でやるとか、聞き取りにくくなってしまいそうな声質を維持したまま口の動きで聞き取れるように工夫するとかやった方が色々試すといい。単音やロングトーン系の発声とかでも、自分でコントロールしにくい声質や音程であえてやってみるといろんなことに気づけるからおすすめ。
5:限界を試す・広げる
声量や音程の限界が人によって違うんで(当たり前か)その限界を認識したり、広げたりする試みは重要。また、別の話として、役柄に応じた声質の「その役柄が喋っていると認識される範囲」の限界値を探るのも有用。この範囲を広げるにはコントロール性を上げる必要があるけど、広いほど「作り声じゃなくて普通に喋ってる」ように聞こえるし、表情豊かな喋りが展開できる。そして失敗すると「別人の喋り」になってしまう。この線引きを行いつつ拡大する。
とりあえずすぐ思いつく範疇で5個あげてみた。やってると他にも「あ、こんなこともやってたな」とか出てきそうだけどって書いてるウチに1個出てきたけどもーいーや。
1日の発声練習の中で、このパートはこれを目的に、ここではこれを目的にって切り替えてもいいし、日毎に変えてもいいし。しばらくの間同じ目的で続けるのもいい。
ウチではルーティンでやってる発声練習の中では、「今日はみんなこれを目的に」とか決めず、各自がそれぞれ自分の目的に応じて勝手にやってる感じですね。声開発系のワークはまた別ですけど。
発声練習って稽古の度にやることが多いと思うんで、問題意識や目的意識のあり方でかなり差が出る。っつーことで、なんとなーくじゃなくて色々やってみてくださいな、と。
と、今回わかりやすく有用っぽい感じの内容になっちゃった反動でどっかの軍曹に出てきてもらいました。
ってことで、なんか向上。なんかっつーか発声練習。
いやどうにもバーチャル・ツール・ド・フランスの楽しみ方がわかんないんすよ。サイクルトレーナーで実際に漕いでるとはいえ「別に本気でやってませんし」「ウチ高地で酸素薄いんで」ってなスタンスのチームや選手も多いから、他人が遊んでるゲーム眺めてるくらいの感じにしかならんのです。
NFLで言うとプレシーズンやプロボウル見てる感じ。やっぱ本気の姿じゃないと楽しめないんだよなー。
ってことで今回は、発声練習本気でやろうぜっていうか。そんな回。
ワークショップで声について扱う場面があると、僕は最初に「発声練習ってやってる?」って聞いてみることが多いです。
まあ、答えはだいたいYesですよ。さすがにワークショップに参加するような人たちですからね、その辺は多少なりともちゃんとしてらっしゃる。
でも「なんのためにやってる?」って聞いてみると、曖昧な答えしか返ってこないことが多いんだなコレが。
ということで、今日は発声練習について考えてみたいと思います。
うん、そうなんだ。
発声そのものについては今週もまとめられなかったんだ。そんな僕に石を投げないでほしい。

まずなにやるにしても目的は持とうね
声を大にして言わせてもらう。いや、声を大にして言わせてもらうためにちょっと発声練習してから声を大にして言わせてもらう。
稽古時間に余裕がねーんだよ目的持たずにやってるくらいなら他のことに時間使わせてくれよコンチクショーメ。
これは多くの演出家が感じているであろう事実である。
とか偉そうに始めてみましたけど、まーね、わからんでもないんですよ。アマチュア団体なんかの発声練習が非常にヌルい感じになるのはだいたい以下の理由だと思う。
・ルーティンとして発声練習やってる
・自分は既にある程度発声ができていると考えている
・そもそも指導者がそれ以上のことを求めてない
そりゃ惰性でやるだけになりますよ。
もちろん、台詞使った稽古やるときは(演出方針によるけど)日常より多少大きな声や口の動きになるんで、その準備体操的な意味合いでやるってのはわかる。わかるんだけど、だとしたら5〜10分もあれば充分でしょう。そのぶん他のことに時間使いましょうやダンナ。
それから、ウォーミングアップ的な意味合いとしてやっているだけなら、別の疑問が湧いてくる。
発声のバリエーション増やしたり磨いたりするための時間はいつ作るつもりなんすか?
っていう。「私は既にこれ以上の向上が見込めないほど素晴らしい発声ができる」と考えてるなら、ぶっちゃけ役者やめた方がいい。「そうじゃないのはわかってるけど発声練習は無目的」なら、それもやっぱり役者やめた方がいい。どっちにしたって現状認識と問題意識、その改善のための考察と実行っていう、役者として必要とされる最上位クラスのものが欠けてるんじゃねーですか、と。
っつーことで、ちゃんと目的意識を持って発声練習してくださいね。
発声練習や発声方法に対する誤った認識
アマチュア団体なんかでよく見かける風景。
台本読みや立ち稽古に入る前に発声練習開始。わりとみんなマジメにやってる。声もしっかり出してる。一息入れて、さあ読み合わせ……
……ん?さっきと発声方法全然ちがうけど?
や、発声練習と台詞読みで声質や発声方法が全然違うの、別に全面的に悪いわけじゃないですよ。発声練習をあくまで準備運動と捉えるならね。
でも準備運動だとするなら、せめて終盤はその舞台で使う声で発声練習やった方がいいんじゃないかな、とは思う。
若干話が逸れるんだけど一応触れておくと、アマチュア団体なんかにありがちな「発声練習の声」と「実際に使う声」が違う現象は、「正しい発声方法」に対する誤解に起因してる気がする。
現在の日本で「正しい発声方法」として説明・紹介されるものは、基本的にオペラやミュージカル、ゴスペルなんかの歌唱用の発声方法がベースになってることが多い。ここに至る歴史的・技術的経緯云々をやりだすと読む方も書く方もメンドクサイのでやめるけど(おぃ)、基本は歌うための発声だからね、ナチュラルな喋りにはなりにくいっていうか、あの声で喋ると「しーんぱーいナイさぁぁぁ」な感じになっちゃうワケ。
だから「発声練習は正しい発声方法で」「でも台詞読みは別」って感じになって、ぶっちゃけ時間かける意味の薄いものになっちゃう。
ボイトレなんかも、先生の経歴によるけど基本は歌用。特に最近はマイク使用を前提としたボイトレも多いんで、そうなってくると生声前提な芝居の現場でダイレクトに使えるものではなかったりする。あと近年じゃ声優用ってのもあるか。声優と舞台の発声方法も全然違うよね。
あ、誤解されそうなので言っておくと、これらの発声方法が間違ってるとか、役に立たないってことではないですよ。
・正しい発声法のひとつではあっても全てではない
・声を開発するにあたって役に立つが、そのまま使える状況は限られる
って感じ。
じゃあ現代の日本における演劇用の正しい発声方法ってなんなのかって言うと、「なんでもいい」。
いやもちろん、「千秋楽の最後の幕が下りるまで保つ(もつ)声であること」とか、「演出上求められる声量でコントロールできること」とか、ある程度の条件はあるけどね。それがどんな条件かってのは演出次第。その条件さえクリアしてればどんな発声方法でもいいんですよ。
実はこれ、発音や発語についても似たようなことが言えて、その辺の指導ってナレーションやアナウンサーのものが基本になってる(しかもラジオ時代に発展したものが中心。加えて言うなら声優系も役者は見えない前提の喋り)。
いずれにしても、正しいやり方のひとつではあっても、全てじゃない。
だから「正しい発声方法はこれ」って考えて「正しい発声方法で発声練習」とか考えなくていいです。
むしろ発声練習では、自分の声の持つ可能性を追求しましょう。
どんな目的を持つか
発声練習の目的やそれによって得られるものってのはひとつではないです。別にいろんな目的があっていいし、それに応じたやり方をすればいい。
まあ、トレーニングってなんでもそういうものでしょ。
1:ウォーミングアップ
否定してたワケじゃねーですよ、と。日常生活から舞台用の幅のある声にいきなり変えるのはなかなか難しいんで、ウォーミングアップを目的とした発声練習は別にアリ。基本そんなに時間かからないので手早く済ませる方法を何パターンかもっておくといいです。
2:役柄の声に慣れる
現在取り組んでいる役柄があって、その声質の方向性が決まっているなら、ある程度その声使って発声練習やった方がいいです。全てをそれでやる必要はないけど、その声質でのコントロール性を上げるなら発声練習が一番いい。というか、この練習を台詞合わせ中にやられても、ぶっちゃけ周りの役者の迷惑にしかならない。
3:新たな声質の開発
芝居はどんな声でもいいってことは、自分の「使える声」を色々持っている方が役者としては有利。これ専用の時間をくれる劇団なんてほとんどないから、発声練習の中で色々試した方がいい。うちの役者はそれなりに舞台経験あるけど、未だに声の開発し続けてる。ありがたい話だ。
4:苦手な部分の克服
ちょっと言い方的に広いんだけど。例えば早口言葉。これ、早く言える言い方でやっても得られるものは多くないんですよ。あえて言いにくい声質でやるとか、聞き取りにくくなってしまいそうな声質を維持したまま口の動きで聞き取れるように工夫するとかやった方が色々試すといい。単音やロングトーン系の発声とかでも、自分でコントロールしにくい声質や音程であえてやってみるといろんなことに気づけるからおすすめ。
5:限界を試す・広げる
声量や音程の限界が人によって違うんで(当たり前か)その限界を認識したり、広げたりする試みは重要。また、別の話として、役柄に応じた声質の「その役柄が喋っていると認識される範囲」の限界値を探るのも有用。この範囲を広げるにはコントロール性を上げる必要があるけど、広いほど「作り声じゃなくて普通に喋ってる」ように聞こえるし、表情豊かな喋りが展開できる。そして失敗すると「別人の喋り」になってしまう。この線引きを行いつつ拡大する。
とりあえずすぐ思いつく範疇で5個あげてみた。やってると他にも「あ、こんなこともやってたな」とか出てきそうだけどって書いてるウチに1個出てきたけどもーいーや。
1日の発声練習の中で、このパートはこれを目的に、ここではこれを目的にって切り替えてもいいし、日毎に変えてもいいし。しばらくの間同じ目的で続けるのもいい。
ウチではルーティンでやってる発声練習の中では、「今日はみんなこれを目的に」とか決めず、各自がそれぞれ自分の目的に応じて勝手にやってる感じですね。声開発系のワークはまた別ですけど。
発声練習って稽古の度にやることが多いと思うんで、問題意識や目的意識のあり方でかなり差が出る。っつーことで、なんとなーくじゃなくて色々やってみてくださいな、と。
いいかオマエら、発声練習ってのはな、戦場だ! 食うか食われるか。プライドをかけた役者たちの熱き戦いなんだ!アホみてーに口開けてボーッと声出してんじゃねえ!そんなヤツは口にパクチー放り込まれると思え!ああ?自分はパクチーが好きです、だぁ?いいか、よく聞け。パクチーの日本名は、カメムシソウだ!パクチーとカメムシは同じ匂いだ!貴様はカメムシが好きなのかこの変態野郎!わかったら気合い入れて発声練習しやがれ!
と、今回わかりやすく有用っぽい感じの内容になっちゃった反動でどっかの軍曹に出てきてもらいました。
ってことで、なんか向上。なんかっつーか発声練習。