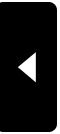2020年07月14日05:46
ちょっと踊ってみましょうか≫
カテゴリー │唐津「なんか向上」
太陽が恋しい(あいさつ)
と言いつつ雨も嫌いじゃない。雨の中でランニングするの意外と好きなんですよ。自宅出発→走り終わってすぐシャワー浴びられるってことなら、水たまりばっちゃんばっちゃんやって走るのなんてむしろ遊び要素。ずぶ濡れになりながら走るバカっぽさも手伝って、うひょーってなります。うひょーって。
童心に返る。
僕がトレラン好きなのもそこなんだろうなー。ひゃーひゃー言いながら走っちゃいますもん。コケるのも笑えるし。終盤のあまりのキツさに笑えてくるし。
Back to 童心。雨きっかけ。れーーーぇーーーぇーーーぇぇぇぇぇーーーぇーーーぃん。I don’t mindってワケ。そこにつながる人とは多分友達になれる。ついでにBack to beautifulにつなげてその真逆さと両者の微妙な共通項にアタマを巡らせはじめる人はもっと好き。
The Beatles - Rain
Sofia Carson - Back to Beautiful
どうでもいい……ことはないか。この2曲の連想は無駄話っつーよりこの時節へのアプローチ……かもしんない。んで、全然関係ない曲や言葉から連想広げて別の何かに思いを馳せる僕の脚本の書き方……って説明を珍しくしてみた次第。
イヤそんな説明こそどうでもえーわ(訛
ということで、童心に返って踊ってみましょうっていう雑な枕。フィジカル系ばっかりやってても飽きると思うんで、ちょっと息抜きに踊ってみよう。

ちなみにうちは基本的に、芝居中に役者がダンスしたりしないです。ごく稀に振り付けみたいなことやりますけどね。でもやっぱ役者ってダンサーじゃないから素敵に踊れないし、僕も素敵な振り付けできないし。不出来なシーンを客前に出すのがイヤっていう単純な理由で、芝居中のダンスはよほどの理由がない限りやらないことにしてる。
っていうと、「ん?わりとけっこう踊ってね?」とか言われたりする。たしかにねー、音楽にあわせて動くってのはよくやるんですよ。でもあれ踊りじゃないのね、振り付けもしてないし。パントマイムとかの延長というか。作ってるとこ見るとわかるんだけど。
文字で書き起こすとこんな感じ。
「ちょっとこのリズムにノッて料理してー。んー、多国籍な雑料理かな。猥雑な感じ。殺伐としつつポップに。あー、そうね、電子レンジとかの類はない方向で。ちなみにスラップスティックなサイレントムービーみたいな早回し風だと?んじゃキック入る時に大きめのアクセント入れて。あーそうね。はいはい。んじゃ次それを奪い合うように貪り食らうお客たちをスローモーションで。いや奪い合うんじゃなくて奪い合うように、だっつーの。んー、じゃ君と君はその隙間を涼しい顔で歩くホール係って感じで……(続」
……振り付けしてない。各自勝手に演技してもらってる。ポイントで誰かの動きを全員にやらせたり、曲のアクセントでなんかやったりするけどね。そんな感じの集合体。なので踊ってない。傍目に踊ってるように見えたとしてもやってる側としては踊ってない。
そんな、舞台では踊らない僕らだけど、稽古ではけっこう踊らせてる。そう、僕の手のひらの上で……って比喩的な意味じゃなく文字どおり踊ってもらってる。
いろんな目的でいろんなやり方で踊るんだけど、よくやるのはこのふたつ。
前者はまあ踊りというよりはムーブメントかな。さっきの料理人みたいにテーマ決めることもあるし、それ自体フリーなこともある。やらせてる間に全然違うジャンルの曲にバンバン切り替えたりする。さっきみたいなシーン作りに直結する感じで、どちらかというと体の使い方云々より発想なんかが問われる。
後者はあくまでダンス。といっても雑でフリーなヤツ。よく海外の映画やドラマでナイトクラブ(日本でいうディスコやクラブ)のシーンなんかに出てくる、テキトーで雑多に踊ってるアレ。あれの激しく踊ってる人みたいな感じ。
前者は演技の延長なのである程度できる役者なら色々やってくれるし、そうでない人でもある程度誤魔化しがきく。できない人が圧倒的に多いのは後者。ダンスってなった瞬間に「踊れない」ってアタマが先に来る。しょうがないからなんとなーく体揺らして誤魔化そうとする。日本のクラブでよく見る光景。踊りに来たんじゃないんかあんたらっていう。
役者は踊れた方がいい。
あ、別にダンス習うとかそういうことじゃないですよ。踊る=ダンス、じゃない……っていうと語弊がある?
なんとかダンス、みたいな型のある踊りは別にできなくてもいいんですよ。イヤもちろんできればそれはそれとして演技の役に立つこともあるだろうけど、別に必須じゃない。ランニングはやった方がいいけどフルマラソン完走は必須じゃないのと同じ。
逆に言うと、型がないと踊れないってのは役者としてはよろしくない。例えばブレイクダンスやってる人でも、ブレイクダンスの技を禁止したら踊れないとか、手振りのアイドルダンスはできるけど馴染みのないジャンルの曲とかかかるとフリーズしちゃうってのは役者としては物足りない。
踊るってのはつまり、楽曲の構成要素やそこから自分が受けたイメージなんかを肉体で表出させるってのが本質……かどうかは知らないけど、ここではそういうことにする(おぃ
や、だって役者が求められるのってそこだからね。イメージを肉体化するっていう。
ダンスのジャンルでいうならいわゆるインプロビゼーション(乱暴に言うと即興のモダンダンス)がアプローチ的に近いんだけど、もっと雑でいい。さっきも言った通り、フロアに集まったぱーりーぴーぽーの中で素敵に踊ってる人くらいな感じ。
ちょっとこの映像見て欲しい。音楽的にどうこうってのもあると思うけどまあそれはおいといて。
https://youtu.be/7BG88HMRVUc
Martin Garrixのわりと初期の映像なんだけど、正直この頃まだ盛り上げ方がうまくない。イヤ彼の名誉のために一応弁護すると、まだヒット曲そんなになかった頃のはずなのでそもそも食いつきがよくないってのもある……はず。最初の自己紹介の殊勝なこと(笑
イマイチ盛り上がらないのが観客行動に現れてて、抜け後の4つ打ちで縦ノリジャンプ→飽きて静まるを繰り返してる。延々見させるのもなんなので典型的なシーンを上げると1:30あたりから。2:10過ぎの4つ打ちで跳ねるんだけど、2:30くらいにはもう飽きはじめて、3:00過ぎあたりから同じこと繰り返す。でもこれも持続できなくて……って感じ。4:30あたりからなんて見てて辛くなるくらい、上げにかかってるのに客席は静まってく。
いやDJ講座をやりたいワケじゃない。
見て欲しいのはむしろ観客側。この手のイベントは騒ぎたいだけの人から踊るのが好きな人まで色々来る。4つ打ちでアホジャンプして他は持て余すっつーのは踊れない人の典型。踊れるし踊りたいけどDJ気に入らねーって人はそこで跳ねないからね。
でも、客席が静まった後も、よく見るとちゃあんと踊ってる人が時々映る。スシ詰め状態なのであんまり動けてないけど、それでも可能な範疇で踊ってる。かっこいい。
こういう「音のイメージの肉体化」が役者はできた方がいい。
ちょっと話逸れるけど、日本って昔から踊らない民族なんですか?いや神楽みたいな古来からの踊りってのはもちろんあるんだけど、型ありきだよね。盆踊りなんかもそう。宴席で舞われる踊りの類も原則的に型がある気がする。
でもまあ、フリーに踊るっつってもある程度基本となるものはあって、それを使いながら音や衝動に任せる感じではあるので、そういう意味じゃ阿波踊りみたいなヤツとかは該当しなくもないような。琉球地方の三線にあわせた踊りとかね。現代の昔でいうと(変な表現だ)ジュリ扇とかパラパラとか。あれが踊りと呼べるかどうかは別問題としてあるけど。
いずれにしてもそういった様式の中でみんなで一緒に楽しむってくらいの感じが、日本人にとっての踊りぽい。生活の中で、嬉しいから踊るとか、酒飲んで盛り上がって踊るとか、ちょっと集まってゲームでもやらね?ってノリで集まって踊るとか、そういう文化は遠い。ないとは言わないけど遠い。幾度かあったディスコブームもそこまでには至らず、一部のぱーりーぴーぽーの騒ぎにしかなってない。
とはいえ日本に限らず、儀式的だったり遊戯的だったりの違いはあれど、歴史の中で一切踊ってこなかった民族ってのもまた、聞いたことがない(かつて踊っていたがなんらかの事情で禁止されて独自の踊りを失った文化なんかはある)。
どこからかの伝播ではなく、世界各地で様々な民族が、誰に言われるわけでもなく踊るようになる。そういう意味で、踊るってのはわりと根源的な欲求のひとつだと思われる。だから、衝動的に踊るってのはある種、人を根源的な部分に戻してくれる気がする。理性を抑えて本能的になりつつ犯罪にはならない(度を過ぎなければね)素敵な行為だ。
すげー脱線してなにが言いたかったかっていうと、これ。日本で自由に踊るって行為が一般化しない大きな理由のひとつであり、踊れない役者が多い理由。
よーするに恥ずかしいワケだ。
フリーに踊るってのは人に見せるのが「踊りの知識や技術」じゃなくてわりと自分の本能に近いとこになる。本能的な部分を人前に晒すってのは日本の伝統の中で、あるいは現代教育の中で、積極的に推奨された行為じゃあない。だから慣れてないし、それゆえ照れる。
別な角度からいうと、自分の本能的なトコ晒した上で「なーんだそんな感じか」とか思われるのはけっこうツラい。「踊りの技術」というより自分自身のイマイチさを指摘される感じになるからね。演技の初心者がアニメやドラマに出てくる典型的なキャラクターを模倣しがちなのはここに起因してる気がしなくもない。自分で考えた自分の演技を否定されるのを怖がるっていう。観客としてみればそんなテンプレートな演技こそいらんのだけどね。
もちろんこれらは、演技する上で邪魔な要素でしかない。役者ってのはどんな演技だろうが求められたら臆面もなく、そしていい感じにやらなきゃいけないからね。
音楽に身を任せながらフリーに踊って、見てくれを気にせず陶酔するトコまで行ってみるって結構な度胸が必要だったりするけど、だからこそ、演技する上で無意識にかけてるブレーキを外すのに効果的というか。メンタルのトレーニングになるってワケ。
だから、それっぽく横揺れして誤魔化すとか、知ってるダンスの形なぞるとかだと意味ない。こうかな?コレだとカッコ悪いかな?とか気にせず、デタラメでもなんでもとにかく本能的に踊るっつーのが重要。
デタラメでいいってのはもちろんなんだけど、それはそれとして。いつまでもデタラメしかできないと繰り返しやる意味はない。自分を晒すっていうハードルを超えたら「それなりに見られる」ようにしよう。
見栄えを整えようと思ったら、自分の肉体を把握する必要が出て来る。たとえば「腕をアタマの上で柔らかく揺らす」とかやってるつもりでも、外から見たらそう見えない可能性がある。各関節や筋肉のバランスや癖など、いろんな要素の中で「アタマで思い描いたイメージと実際の動きが一致しない」ってことは多々起きるからね。
これは演技してる時でも同じ。役者がどういう意識やイメージで動いてるかは、観客にとってはどうでもいい。観客は自分が直接見てる情報からその裏を想像・推察するんだから「観客にどう見えてるか」がすべてなワケ。
だから、自分のイメージと実際の動きのズレを常に修正していく必要がある。これはガチのダンサーさんたちでさえ一生かけて改善してくようなものなので、ちょっとやそっとで「できた」とか思わない方がいい。いつだって「多少マシになった」程度だと思おう。
踊るってのは常に「体重を支えてる部分から、体重を抜く」って行動の繰り返しになる。
ちょっと立ってみましょうか。立てたら、左足軽く持ち上げます。そうすると全体重が右足にかかる。このままだと、左足は動かせても右足は動かせない。右足を動かすにはどうしよう。
一番簡単なのは、左足を下ろしてそっちに体重移すことだね。あたりまえか。じゃあ、左足下ろさずに右足動かすには?
やり方はいくつかある。例えば右足で軽く飛び跳ねれば、空中にいるあいだ右足にかかってた体重がなくなる。その間に別の場所に足を動かせばいい……ってケンケンだね。他にも、上に飛ぶんじゃなくて膝を曲げることで瞬間的に体重抜くとか、右足を前と後ろに分割して踵に体重かけてる間につま先を移動させ……とか。色々ある。
いずれにしても、重力がある以上体はどこかで支えなきゃいけない&その支えてる部位からなんらかしらの形で体重を移してあげないと、動けない。この時、どこからどっちにどういう方法で体重を移すかってのが踊る時の基礎になる。ステップってのはその組み合わせパターン。
いろんなステップを覚えていろんな体重移動の方法を身につけるってのは役者にとってすごくためになる。なので興味のある人はダンススクールでも通って覚えてください。
が、覚えたステップの組み合わせで踊るなんてのはむしろ今回やりたいことと逆。ヒップホップ系のステップ癖ある人はそれ以外ができなかったりもする。アダージョみたいなゆったり古典舞踊系、5拍子7拍子11拍子なんかが使われまくる変態プログレ、そもそも拍子って概念が希薄なアフリカ民族音楽、みたいな選曲で撃沈。わかりやすい。
ステップはステップで重要だけど、それだけじゃ本能的に踊ってるとは言い難い。
ある程度面白く踊るには、そこでかかってる音楽からなにかを受け取らなくちゃいけない。それを無視して自分のやり方しかやろうとしないってのは役者として致命的な弱点。そういうスタンスって演技にそのまま出るからね。
いろんなジャンルのダンスを覚えて即座に対応ってことじゃないですよ。それは知識で回してるだけなので。跳ねるような元気系ヒップホップがかかったからって、ヒップホップのステップ踏む必要はないです(いや踏んでもいいけども)。ヒップホップ特有のタメなんかを感じて曲に合うように跳ねるとか、その弾性を肌で感じながらサンプリングされたストリングスに合わせて心地よさげに滑らかに腕を揺らすとか、別になんでもいい。
ようは音楽を聴いて反応するってことでしかないんだけど、そのためにはやっぱある程度音楽的な知識は必要になってくる。
音楽が好きって人は多いと思うけど、じゃあどれくらい聞いてるかっていうとほとんどの人はその幅が超狭い。いや、自分の好きなジャンルやアーティストって大事よ。でもいろんな地域やジャンルの音楽聴いた方がいい。ん?俺は結構聴いてるぜって?オーケー、アゼルバイジャンで人気のヘビメタバンドをひとつ教えてくれないか?
ってのは冗談としても、音楽ジャンルを表す用語ってどれくらい知ってるだろう。けっこう山ほどあるよね。ゴアってなんのサブジャンル?とか。60年代のビートルズやストーンズってジャンルとしては何ていう?とかね。
ちなみに前者の答えはトランス。後者はマージービート(ブリティッシュ・ロックとか第一次ブリティッシュ・インベイションってのはジャンル名じゃないからね)。
地域的にとらえてみても、日本、アメリカ、イギリス、あと最近だと韓国あたりかな、それ以外の国のアーティストどれくらい知ってるだろう。それぞれの国に、国民的アーティストが一人くらいいるわけじゃん。
自分の考える「いろんな音楽」ってのは実は結構幅狭い。自分の好きなジャンルを掘り下げるっていう音楽の聴き方もいいんだけど、まだまだ知らないジャンルやアーティストの方が多いんだよね。
ひとつのジャンルを形成するような音楽性、ひとつの国を代表するようなアーティストってのは、なんらかしらの良さを持ってる。その良さを自分が気にいるかどうかは別の話として、多くの人に受け入れられた良さではあるワケ。だからいろんな時代のいろんな人たちのいろんな感性に触れる方法のひとつとして、いろんな音楽を聴こう。で、そこからいろんなものを受け取ってみよう。それは間違いなく役者としての感性を豊かにしてくれる。
まあ音楽だけじゃなく小説や映画、芝居にも言えることだけどね。
いやー、なんかハードル上げただけの投稿になっちゃったかな。でもまあ、基本は音楽聴いてあとは本能的な衝動に任せりゃいいんすよ。ぱーりーぴーぽーの激しめ陶酔ダンス。それを豊かにするための説明しただけ。
いろんな知識や技術を仕入れた上での、感性に任せたムーブメント。これ結局、演技のプロセスと同じなのね。
なので踊り、しかもフリーに踊るってのは、以前三角形で示した「基礎」→「知識・技術」→「感性」のすべてに大きな刺激をくれる。肉体が持つ音楽性のバリエーションが増えると台詞読みなんかも豊かになるし、ぶっちゃけイイことしかない。
なので日頃からいろんな音楽でテキトーに踊るとか、逆に知識や技術をインストールするとかやってるといいです。役者としての色気や面白みがでてきます。YoutubeでもSpotifyでもなんでもいいから、知らない世界にレッツゴー。
ってなことで、なんか向上でした。多分感性。
と言いつつ雨も嫌いじゃない。雨の中でランニングするの意外と好きなんですよ。自宅出発→走り終わってすぐシャワー浴びられるってことなら、水たまりばっちゃんばっちゃんやって走るのなんてむしろ遊び要素。ずぶ濡れになりながら走るバカっぽさも手伝って、うひょーってなります。うひょーって。
童心に返る。
僕がトレラン好きなのもそこなんだろうなー。ひゃーひゃー言いながら走っちゃいますもん。コケるのも笑えるし。終盤のあまりのキツさに笑えてくるし。
Back to 童心。雨きっかけ。れーーーぇーーーぇーーーぇぇぇぇぇーーーぇーーーぃん。I don’t mindってワケ。そこにつながる人とは多分友達になれる。ついでにBack to beautifulにつなげてその真逆さと両者の微妙な共通項にアタマを巡らせはじめる人はもっと好き。
The Beatles - Rain
Sofia Carson - Back to Beautiful
どうでもいい……ことはないか。この2曲の連想は無駄話っつーよりこの時節へのアプローチ……かもしんない。んで、全然関係ない曲や言葉から連想広げて別の何かに思いを馳せる僕の脚本の書き方……って説明を珍しくしてみた次第。
イヤそんな説明こそどうでもえーわ(訛
ということで、童心に返って踊ってみましょうっていう雑な枕。フィジカル系ばっかりやってても飽きると思うんで、ちょっと息抜きに踊ってみよう。

踊らないのに踊るカラクリさんたち
ちなみにうちは基本的に、芝居中に役者がダンスしたりしないです。ごく稀に振り付けみたいなことやりますけどね。でもやっぱ役者ってダンサーじゃないから素敵に踊れないし、僕も素敵な振り付けできないし。不出来なシーンを客前に出すのがイヤっていう単純な理由で、芝居中のダンスはよほどの理由がない限りやらないことにしてる。
っていうと、「ん?わりとけっこう踊ってね?」とか言われたりする。たしかにねー、音楽にあわせて動くってのはよくやるんですよ。でもあれ踊りじゃないのね、振り付けもしてないし。パントマイムとかの延長というか。作ってるとこ見るとわかるんだけど。
文字で書き起こすとこんな感じ。
「ちょっとこのリズムにノッて料理してー。んー、多国籍な雑料理かな。猥雑な感じ。殺伐としつつポップに。あー、そうね、電子レンジとかの類はない方向で。ちなみにスラップスティックなサイレントムービーみたいな早回し風だと?んじゃキック入る時に大きめのアクセント入れて。あーそうね。はいはい。んじゃ次それを奪い合うように貪り食らうお客たちをスローモーションで。いや奪い合うんじゃなくて奪い合うように、だっつーの。んー、じゃ君と君はその隙間を涼しい顔で歩くホール係って感じで……(続」
……振り付けしてない。各自勝手に演技してもらってる。ポイントで誰かの動きを全員にやらせたり、曲のアクセントでなんかやったりするけどね。そんな感じの集合体。なので踊ってない。傍目に踊ってるように見えたとしてもやってる側としては踊ってない。
そんな、舞台では踊らない僕らだけど、稽古ではけっこう踊らせてる。そう、僕の手のひらの上で……って比喩的な意味じゃなく文字どおり踊ってもらってる。
いろんな目的でいろんなやり方で踊るんだけど、よくやるのはこのふたつ。
・曲のイメージで動く
・フリーな踊り
前者はまあ踊りというよりはムーブメントかな。さっきの料理人みたいにテーマ決めることもあるし、それ自体フリーなこともある。やらせてる間に全然違うジャンルの曲にバンバン切り替えたりする。さっきみたいなシーン作りに直結する感じで、どちらかというと体の使い方云々より発想なんかが問われる。
後者はあくまでダンス。といっても雑でフリーなヤツ。よく海外の映画やドラマでナイトクラブ(日本でいうディスコやクラブ)のシーンなんかに出てくる、テキトーで雑多に踊ってるアレ。あれの激しく踊ってる人みたいな感じ。
前者は演技の延長なのである程度できる役者なら色々やってくれるし、そうでない人でもある程度誤魔化しがきく。できない人が圧倒的に多いのは後者。ダンスってなった瞬間に「踊れない」ってアタマが先に来る。しょうがないからなんとなーく体揺らして誤魔化そうとする。日本のクラブでよく見る光景。踊りに来たんじゃないんかあんたらっていう。
ぱーりーぴーぽー
役者は踊れた方がいい。
あ、別にダンス習うとかそういうことじゃないですよ。踊る=ダンス、じゃない……っていうと語弊がある?
なんとかダンス、みたいな型のある踊りは別にできなくてもいいんですよ。イヤもちろんできればそれはそれとして演技の役に立つこともあるだろうけど、別に必須じゃない。ランニングはやった方がいいけどフルマラソン完走は必須じゃないのと同じ。
逆に言うと、型がないと踊れないってのは役者としてはよろしくない。例えばブレイクダンスやってる人でも、ブレイクダンスの技を禁止したら踊れないとか、手振りのアイドルダンスはできるけど馴染みのないジャンルの曲とかかかるとフリーズしちゃうってのは役者としては物足りない。
踊るってのはつまり、楽曲の構成要素やそこから自分が受けたイメージなんかを肉体で表出させるってのが本質……かどうかは知らないけど、ここではそういうことにする(おぃ
や、だって役者が求められるのってそこだからね。イメージを肉体化するっていう。
ダンスのジャンルでいうならいわゆるインプロビゼーション(乱暴に言うと即興のモダンダンス)がアプローチ的に近いんだけど、もっと雑でいい。さっきも言った通り、フロアに集まったぱーりーぴーぽーの中で素敵に踊ってる人くらいな感じ。
ちょっとこの映像見て欲しい。音楽的にどうこうってのもあると思うけどまあそれはおいといて。
https://youtu.be/7BG88HMRVUc
Martin Garrixのわりと初期の映像なんだけど、正直この頃まだ盛り上げ方がうまくない。イヤ彼の名誉のために一応弁護すると、まだヒット曲そんなになかった頃のはずなのでそもそも食いつきがよくないってのもある……はず。最初の自己紹介の殊勝なこと(笑
イマイチ盛り上がらないのが観客行動に現れてて、抜け後の4つ打ちで縦ノリジャンプ→飽きて静まるを繰り返してる。延々見させるのもなんなので典型的なシーンを上げると1:30あたりから。2:10過ぎの4つ打ちで跳ねるんだけど、2:30くらいにはもう飽きはじめて、3:00過ぎあたりから同じこと繰り返す。でもこれも持続できなくて……って感じ。4:30あたりからなんて見てて辛くなるくらい、上げにかかってるのに客席は静まってく。
いやDJ講座をやりたいワケじゃない。
見て欲しいのはむしろ観客側。この手のイベントは騒ぎたいだけの人から踊るのが好きな人まで色々来る。4つ打ちでアホジャンプして他は持て余すっつーのは踊れない人の典型。踊れるし踊りたいけどDJ気に入らねーって人はそこで跳ねないからね。
でも、客席が静まった後も、よく見るとちゃあんと踊ってる人が時々映る。スシ詰め状態なのであんまり動けてないけど、それでも可能な範疇で踊ってる。かっこいい。
こういう「音のイメージの肉体化」が役者はできた方がいい。
踊る文化が遠い現代日本
ちょっと話逸れるけど、日本って昔から踊らない民族なんですか?いや神楽みたいな古来からの踊りってのはもちろんあるんだけど、型ありきだよね。盆踊りなんかもそう。宴席で舞われる踊りの類も原則的に型がある気がする。
でもまあ、フリーに踊るっつってもある程度基本となるものはあって、それを使いながら音や衝動に任せる感じではあるので、そういう意味じゃ阿波踊りみたいなヤツとかは該当しなくもないような。琉球地方の三線にあわせた踊りとかね。現代の昔でいうと(変な表現だ)ジュリ扇とかパラパラとか。あれが踊りと呼べるかどうかは別問題としてあるけど。
いずれにしてもそういった様式の中でみんなで一緒に楽しむってくらいの感じが、日本人にとっての踊りぽい。生活の中で、嬉しいから踊るとか、酒飲んで盛り上がって踊るとか、ちょっと集まってゲームでもやらね?ってノリで集まって踊るとか、そういう文化は遠い。ないとは言わないけど遠い。幾度かあったディスコブームもそこまでには至らず、一部のぱーりーぴーぽーの騒ぎにしかなってない。
とはいえ日本に限らず、儀式的だったり遊戯的だったりの違いはあれど、歴史の中で一切踊ってこなかった民族ってのもまた、聞いたことがない(かつて踊っていたがなんらかの事情で禁止されて独自の踊りを失った文化なんかはある)。
どこからかの伝播ではなく、世界各地で様々な民族が、誰に言われるわけでもなく踊るようになる。そういう意味で、踊るってのはわりと根源的な欲求のひとつだと思われる。だから、衝動的に踊るってのはある種、人を根源的な部分に戻してくれる気がする。理性を抑えて本能的になりつつ犯罪にはならない(度を過ぎなければね)素敵な行為だ。
照れ
すげー脱線してなにが言いたかったかっていうと、これ。日本で自由に踊るって行為が一般化しない大きな理由のひとつであり、踊れない役者が多い理由。
よーするに恥ずかしいワケだ。
フリーに踊るってのは人に見せるのが「踊りの知識や技術」じゃなくてわりと自分の本能に近いとこになる。本能的な部分を人前に晒すってのは日本の伝統の中で、あるいは現代教育の中で、積極的に推奨された行為じゃあない。だから慣れてないし、それゆえ照れる。
別な角度からいうと、自分の本能的なトコ晒した上で「なーんだそんな感じか」とか思われるのはけっこうツラい。「踊りの技術」というより自分自身のイマイチさを指摘される感じになるからね。演技の初心者がアニメやドラマに出てくる典型的なキャラクターを模倣しがちなのはここに起因してる気がしなくもない。自分で考えた自分の演技を否定されるのを怖がるっていう。観客としてみればそんなテンプレートな演技こそいらんのだけどね。
もちろんこれらは、演技する上で邪魔な要素でしかない。役者ってのはどんな演技だろうが求められたら臆面もなく、そしていい感じにやらなきゃいけないからね。
音楽に身を任せながらフリーに踊って、見てくれを気にせず陶酔するトコまで行ってみるって結構な度胸が必要だったりするけど、だからこそ、演技する上で無意識にかけてるブレーキを外すのに効果的というか。メンタルのトレーニングになるってワケ。
だから、それっぽく横揺れして誤魔化すとか、知ってるダンスの形なぞるとかだと意味ない。こうかな?コレだとカッコ悪いかな?とか気にせず、デタラメでもなんでもとにかく本能的に踊るっつーのが重要。
肉体を知る
デタラメでいいってのはもちろんなんだけど、それはそれとして。いつまでもデタラメしかできないと繰り返しやる意味はない。自分を晒すっていうハードルを超えたら「それなりに見られる」ようにしよう。
見栄えを整えようと思ったら、自分の肉体を把握する必要が出て来る。たとえば「腕をアタマの上で柔らかく揺らす」とかやってるつもりでも、外から見たらそう見えない可能性がある。各関節や筋肉のバランスや癖など、いろんな要素の中で「アタマで思い描いたイメージと実際の動きが一致しない」ってことは多々起きるからね。
これは演技してる時でも同じ。役者がどういう意識やイメージで動いてるかは、観客にとってはどうでもいい。観客は自分が直接見てる情報からその裏を想像・推察するんだから「観客にどう見えてるか」がすべてなワケ。
だから、自分のイメージと実際の動きのズレを常に修正していく必要がある。これはガチのダンサーさんたちでさえ一生かけて改善してくようなものなので、ちょっとやそっとで「できた」とか思わない方がいい。いつだって「多少マシになった」程度だと思おう。
体重移動のスキルアップ
踊るってのは常に「体重を支えてる部分から、体重を抜く」って行動の繰り返しになる。
ちょっと立ってみましょうか。立てたら、左足軽く持ち上げます。そうすると全体重が右足にかかる。このままだと、左足は動かせても右足は動かせない。右足を動かすにはどうしよう。
一番簡単なのは、左足を下ろしてそっちに体重移すことだね。あたりまえか。じゃあ、左足下ろさずに右足動かすには?
やり方はいくつかある。例えば右足で軽く飛び跳ねれば、空中にいるあいだ右足にかかってた体重がなくなる。その間に別の場所に足を動かせばいい……ってケンケンだね。他にも、上に飛ぶんじゃなくて膝を曲げることで瞬間的に体重抜くとか、右足を前と後ろに分割して踵に体重かけてる間につま先を移動させ……とか。色々ある。
いずれにしても、重力がある以上体はどこかで支えなきゃいけない&その支えてる部位からなんらかしらの形で体重を移してあげないと、動けない。この時、どこからどっちにどういう方法で体重を移すかってのが踊る時の基礎になる。ステップってのはその組み合わせパターン。
いろんなステップを覚えていろんな体重移動の方法を身につけるってのは役者にとってすごくためになる。なので興味のある人はダンススクールでも通って覚えてください。
が、覚えたステップの組み合わせで踊るなんてのはむしろ今回やりたいことと逆。ヒップホップ系のステップ癖ある人はそれ以外ができなかったりもする。アダージョみたいなゆったり古典舞踊系、5拍子7拍子11拍子なんかが使われまくる変態プログレ、そもそも拍子って概念が希薄なアフリカ民族音楽、みたいな選曲で撃沈。わかりやすい。
ステップはステップで重要だけど、それだけじゃ本能的に踊ってるとは言い難い。
音楽的な知識と感受性
ある程度面白く踊るには、そこでかかってる音楽からなにかを受け取らなくちゃいけない。それを無視して自分のやり方しかやろうとしないってのは役者として致命的な弱点。そういうスタンスって演技にそのまま出るからね。
いろんなジャンルのダンスを覚えて即座に対応ってことじゃないですよ。それは知識で回してるだけなので。跳ねるような元気系ヒップホップがかかったからって、ヒップホップのステップ踏む必要はないです(いや踏んでもいいけども)。ヒップホップ特有のタメなんかを感じて曲に合うように跳ねるとか、その弾性を肌で感じながらサンプリングされたストリングスに合わせて心地よさげに滑らかに腕を揺らすとか、別になんでもいい。
ようは音楽を聴いて反応するってことでしかないんだけど、そのためにはやっぱある程度音楽的な知識は必要になってくる。
音楽が好きって人は多いと思うけど、じゃあどれくらい聞いてるかっていうとほとんどの人はその幅が超狭い。いや、自分の好きなジャンルやアーティストって大事よ。でもいろんな地域やジャンルの音楽聴いた方がいい。ん?俺は結構聴いてるぜって?オーケー、アゼルバイジャンで人気のヘビメタバンドをひとつ教えてくれないか?
ってのは冗談としても、音楽ジャンルを表す用語ってどれくらい知ってるだろう。けっこう山ほどあるよね。ゴアってなんのサブジャンル?とか。60年代のビートルズやストーンズってジャンルとしては何ていう?とかね。
ちなみに前者の答えはトランス。後者はマージービート(ブリティッシュ・ロックとか第一次ブリティッシュ・インベイションってのはジャンル名じゃないからね)。
地域的にとらえてみても、日本、アメリカ、イギリス、あと最近だと韓国あたりかな、それ以外の国のアーティストどれくらい知ってるだろう。それぞれの国に、国民的アーティストが一人くらいいるわけじゃん。
自分の考える「いろんな音楽」ってのは実は結構幅狭い。自分の好きなジャンルを掘り下げるっていう音楽の聴き方もいいんだけど、まだまだ知らないジャンルやアーティストの方が多いんだよね。
ひとつのジャンルを形成するような音楽性、ひとつの国を代表するようなアーティストってのは、なんらかしらの良さを持ってる。その良さを自分が気にいるかどうかは別の話として、多くの人に受け入れられた良さではあるワケ。だからいろんな時代のいろんな人たちのいろんな感性に触れる方法のひとつとして、いろんな音楽を聴こう。で、そこからいろんなものを受け取ってみよう。それは間違いなく役者としての感性を豊かにしてくれる。
まあ音楽だけじゃなく小説や映画、芝居にも言えることだけどね。
ってことで、踊りましょうか
いやー、なんかハードル上げただけの投稿になっちゃったかな。でもまあ、基本は音楽聴いてあとは本能的な衝動に任せりゃいいんすよ。ぱーりーぴーぽーの激しめ陶酔ダンス。それを豊かにするための説明しただけ。
いろんな知識や技術を仕入れた上での、感性に任せたムーブメント。これ結局、演技のプロセスと同じなのね。
なので踊り、しかもフリーに踊るってのは、以前三角形で示した「基礎」→「知識・技術」→「感性」のすべてに大きな刺激をくれる。肉体が持つ音楽性のバリエーションが増えると台詞読みなんかも豊かになるし、ぶっちゃけイイことしかない。
なので日頃からいろんな音楽でテキトーに踊るとか、逆に知識や技術をインストールするとかやってるといいです。役者としての色気や面白みがでてきます。YoutubeでもSpotifyでもなんでもいいから、知らない世界にレッツゴー。
ってなことで、なんか向上でした。多分感性。