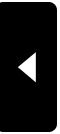2020年12月25日13:33
メリークリスマス!
まさかクリスマスに稽古場日記を書くとは思いませんでした。
でもね、せっかくなので今日はクリスマス特別編。サンタさんになったつもりできゅんからの質問、問21に真剣に答えたいと思います。うまくなるためのクリスマスプレゼント!
(問20はどうした?ってツッコミは受け付けません笑)

前々から言っていることではあるんですが、役者は色んな役(キャラクター)を演じられたほうがいいです。何をやっても同じような役になってしまう役者は、演じられる種類が極端に少ないということになります。そういう役者は演出家から起用されません。よっぽどのハマり役がない限り、大抵は起用されず観客にも飽きられます。
なので役者は引き出しが多い方がいい。

まずは引き出しを増やします。分かりやすくいうと「明るい人」と「暗い人」だったり、「大人しい人」と「活発な人」だったり、そういう引き出しを増やしていきます。
最初のうちはこういう分かりやすい区分けでいいと思います。正反対のものの引き出しを増やすのがやりやすいです。これをやると演じる役が増えて楽しくなりますから。楽しんで引き出しを増やして下さい。ただ、数年役者をしていると気づきます。「あれ、私の引き出しって10個くらいしかなくない?」
なんかね、増えてるようで微妙に増えてないことに気づくんですよ。でね、焦るんです。でもこれに気づいて焦ることが出来る役者は見込みあり!次のステップです。
微妙に増えてないと感じる原因は、「引き出し」そのものではなく「引き出しの中身」が増えてるからなんです。
例えば先ほど例に挙げた「明るい人」で考えてみます。明るい人と一言で言っても色んなタイプの明るい人がいますよね。年齢によっても違うでしょうし、職種や国籍、IQなど様々な要因で明るさは変わってきます。
いわゆる、演じるキャラクターの背景によって明るさは変わるわけです。
ここで先ほどの気づきを持った役者は焦るわけです。明るい役は出来るし、色んな明るい役を演じてきたつもりだったけど、結局どれも似てるんじゃないか、と。
はい、その通りです!
これは「明るい人」という引き出しの中身が増えてるだけなんです。でもそれはダメなことではないんです。いいことなんです。
一つの引き出しの中に中身が一つしかない役者は、キャラクターの背景まで表現することが出来ません。なので何をやっても同じような役になっていくんです。
引き出しそのものを増やしつつ、その中身も増やしていくことが大事になります。

役者は役を与えられたら、演出家にこの引き出しと引き出しの中身を全部をさらけ出すことになります。演出家が探すものを提示出来ればいいですけど、引き出しが少なかったり中身がスカスカだったりすると演出家は隠すことなくその落胆を表情に出します。そして役者は落ち込みます。
余談ですけど、この時の演出家ってホント露骨に落胆します。隠す演出家に会ったことなんてないです。頭を抱えてしまわれる演出家もいますし、スリッパをお投げになる演出家もいます。
では、どうしたらこの引き出しや中身を増やすことが出来るのか。
それは今までの稽古場日記で書いてきた通り「身体」と「感性」を磨くことだと私は思っています。地味な作業なんですよ、意外と(笑)。台本を読み込んで分析したところで引き出しが増えるわけではないんです。自分の身体を表現できるだけの身体に鍛え上げることと、様々なモノに触れて感性を磨き上げること。それだけです。
引き出しの中身が増えたら次のステップ。引き出しの中身を組み合わせる作業に入ります。
これは舞台照明で例えると分かりやすいかなって思います。カラクリの舞台照明って、実に様々な色が組み合わされてるのはご存知でしょうか。

ちょっと照明の話になりますが、照明に色をつけたい時にはカラーフィルターを照明につけてるんです。「ゼラ」とか「色」って呼ばれてるやつですね。
このカラーフィルターってたくさん種類がありまして、青系のものだけでも紫に近い青だったり、緑に近い青だったり、と10種類以上あるんです。
例えば舞台全体を青色のイメージにしたい時、一つの色だけで青を表現することはまずないです。これは前の稽古場日記で載せたライトアップ写真が分かりやすいですね。

1つの色で表現するとこんな感じ。カラクリの舞台と違うのって何となくわかるでしょうか。舞台照明の場合、例えば青いイメージだったとしても様々な色を組み合わせてそれを表現します。
青系の色でも別の色味をものを組み合わせたり、赤や黄色などの全然別の色を織り交ぜたり、そうすることでより青いイメージの舞台を作り上げていくんです。
役者も同じです。引き出しの中身を一つだけ使っている場合、非常に単調な演技になっていきます。かといってシーンごとに引き出しの中身を変えるとキャラクターが崩壊します。
なので引き出しの中身をいくつか組み合わせて役作りをした方が深みが出やすいし、より人間味溢れるキャラクターになります。引き出しの中身は1つのキャラクターにつき最低でも5個くらいは使った方がいいかなって思います。
と、簡単に言ってしまいましたが、この組み合わせで躓く役者がすごく多いと思うんですよね。
引き出しと引き出しの中身を増やすのも大変なんですけど、そこまでできた役者が次に足踏みするのが絶対ここだと思います。うまく組み合わせられるときもあるんですけど、意外と似たようなものの組み合わせが結構難しいんですよね。
どうしたら出来るようになるかって言われるとすごく答えにくいんですけど、何というか、引き出しの中身をきっちり整理するって感じですかね。
曖昧な区分けにしておくと、組み合わせた時に調整がきかなくなると思うんですよ。いつでもその引き出しの中身を完璧に取り出せるように身体と感性を鍛えておくしかないんじゃないかと。うん、やっぱり大事なのはそこですね。
問21「いわゆる「普通の女性」のミランダ役、めっちゃ難しかったと思うんですけど、気を付けたところを10個教えてください。」
引き出しと引き出しの中身を増やして、組み合わせも自由に出来るようになったらいよいよ最終段階。ボリュームの調整です。
ここでも照明に例えて話しますね。
舞台上にどの色をどれくらい当てるかというのは、全部ボリュームで決めています。例えば、このライトはボリューム2でこのライトはボリューム8、このライトは消しておいて、ここにこの色をボリューム5で当てる……みたいな感じです。
この作業をシーンによって、あるいはシーンの途中でもどんどん切り替えていくのがカラクリの舞台照明です。青い照明の中にも赤い色や緑色も入っていたりして、その比率もどんどん変わっていきます。気づくと赤色がメインの舞台に変わっていたり、いつの間にか昼間から夜の雰囲気に舞台が変わっていたりするわけです。
で、役者におけるボリュームの話。

役者のキャラクター作りも同じです。引き出しの中から引き出しの中身を選び組み合わせを決めたら、それぞれをどのくらいのボリュームで出すのかが次のステップになります。
役を演じる時は複数の引き出しの中身を組み合わせた方がいいって話をしましたよね。それぞれの引き出しの中身は、照明同様、シーンによってそのボリュームが変わるわけです。このボリュームがONかOFFしかないと細かい調整が出来ないんです。
ボリュームは細かく設定できる方が絶対いいです。携帯みたいに段階でボリュームが変わるものよりも、手動で細かい調整ができるものの方が自分好みの調整をしやすいのと一緒です。
「普通の女性」であるミランダを演じた時に1番気を付けたことがまさにこのボリュームなんです。
引き出しの中身も結構使いましたし、そのシーンにだけスパイス的な感じで使った引き出しの中身とかもありました。そしてそれを全部コントロールするためのボリューム調整が本当に細かかったことを覚えてます。このシーンでは引き出しの中身Aはボリューム3で、引き出しの中身Bはボリューム8、Cは1くらいで、Dを一回10にあげてそのあと6に落とそうかな、みたいな感じです。
「普通」であるということは、観客が気づいた時にはすでに変わっていたと印象を持たせることが大事です。ボリューム調整をしながら、少しずつ確実に変化させていくんです。決して劇的に変わるのではなく、いつの間にか変わってたんだけども何が変わったのかよく分からないくらいの微調整をしないといけない。
どの引き出しの中身をどのタイミングでどのくらいのボリュームにするのか。引き出しの中身を吟味して、時には中身を減らしたり加えたりしながら微調整をしていく。
どの役を演じる時にも同じなんですけどね、「普通である」という表現をするためにはいつも以上のボリューム調整が必要がでした。
なのできゅん。
今回の質問の答え、10個もありません。
問21「いわゆる「普通の女性」のミランダ役、めっちゃ難しかったと思うんですけど、気を付けたところを10個教えてください。」
解答 細かいボリューム調整 以上
サンタクロース気分で解答21。≫
カテゴリー │中西「きゅんの質問に応えてあげよう!」
from show-co
メリークリスマス!
まさかクリスマスに稽古場日記を書くとは思いませんでした。
でもね、せっかくなので今日はクリスマス特別編。サンタさんになったつもりできゅんからの質問、問21に真剣に答えたいと思います。うまくなるためのクリスマスプレゼント!
(問20はどうした?ってツッコミは受け付けません笑)
役者に必要なもの
前々から言っていることではあるんですが、役者は色んな役(キャラクター)を演じられたほうがいいです。何をやっても同じような役になってしまう役者は、演じられる種類が極端に少ないということになります。そういう役者は演出家から起用されません。よっぽどのハマり役がない限り、大抵は起用されず観客にも飽きられます。
なので役者は引き出しが多い方がいい。
まずは引き出しを増やします。分かりやすくいうと「明るい人」と「暗い人」だったり、「大人しい人」と「活発な人」だったり、そういう引き出しを増やしていきます。
最初のうちはこういう分かりやすい区分けでいいと思います。正反対のものの引き出しを増やすのがやりやすいです。これをやると演じる役が増えて楽しくなりますから。楽しんで引き出しを増やして下さい。ただ、数年役者をしていると気づきます。「あれ、私の引き出しって10個くらいしかなくない?」
なんかね、増えてるようで微妙に増えてないことに気づくんですよ。でね、焦るんです。でもこれに気づいて焦ることが出来る役者は見込みあり!次のステップです。
引き出しの中身
微妙に増えてないと感じる原因は、「引き出し」そのものではなく「引き出しの中身」が増えてるからなんです。
例えば先ほど例に挙げた「明るい人」で考えてみます。明るい人と一言で言っても色んなタイプの明るい人がいますよね。年齢によっても違うでしょうし、職種や国籍、IQなど様々な要因で明るさは変わってきます。
いわゆる、演じるキャラクターの背景によって明るさは変わるわけです。
ここで先ほどの気づきを持った役者は焦るわけです。明るい役は出来るし、色んな明るい役を演じてきたつもりだったけど、結局どれも似てるんじゃないか、と。
はい、その通りです!
これは「明るい人」という引き出しの中身が増えてるだけなんです。でもそれはダメなことではないんです。いいことなんです。
一つの引き出しの中に中身が一つしかない役者は、キャラクターの背景まで表現することが出来ません。なので何をやっても同じような役になっていくんです。
引き出しそのものを増やしつつ、その中身も増やしていくことが大事になります。
役者は役を与えられたら、演出家にこの引き出しと引き出しの中身を全部をさらけ出すことになります。演出家が探すものを提示出来ればいいですけど、引き出しが少なかったり中身がスカスカだったりすると演出家は隠すことなくその落胆を表情に出します。そして役者は落ち込みます。
余談ですけど、この時の演出家ってホント露骨に落胆します。隠す演出家に会ったことなんてないです。頭を抱えてしまわれる演出家もいますし、スリッパをお投げになる演出家もいます。
では、どうしたらこの引き出しや中身を増やすことが出来るのか。
それは今までの稽古場日記で書いてきた通り「身体」と「感性」を磨くことだと私は思っています。地味な作業なんですよ、意外と(笑)。台本を読み込んで分析したところで引き出しが増えるわけではないんです。自分の身体を表現できるだけの身体に鍛え上げることと、様々なモノに触れて感性を磨き上げること。それだけです。
まだまだステップは続きます
引き出しの中身が増えたら次のステップ。引き出しの中身を組み合わせる作業に入ります。
これは舞台照明で例えると分かりやすいかなって思います。カラクリの舞台照明って、実に様々な色が組み合わされてるのはご存知でしょうか。

ちょっと照明の話になりますが、照明に色をつけたい時にはカラーフィルターを照明につけてるんです。「ゼラ」とか「色」って呼ばれてるやつですね。
このカラーフィルターってたくさん種類がありまして、青系のものだけでも紫に近い青だったり、緑に近い青だったり、と10種類以上あるんです。
例えば舞台全体を青色のイメージにしたい時、一つの色だけで青を表現することはまずないです。これは前の稽古場日記で載せたライトアップ写真が分かりやすいですね。

1つの色で表現するとこんな感じ。カラクリの舞台と違うのって何となくわかるでしょうか。舞台照明の場合、例えば青いイメージだったとしても様々な色を組み合わせてそれを表現します。
青系の色でも別の色味をものを組み合わせたり、赤や黄色などの全然別の色を織り交ぜたり、そうすることでより青いイメージの舞台を作り上げていくんです。
役者も同じです。引き出しの中身を一つだけ使っている場合、非常に単調な演技になっていきます。かといってシーンごとに引き出しの中身を変えるとキャラクターが崩壊します。
なので引き出しの中身をいくつか組み合わせて役作りをした方が深みが出やすいし、より人間味溢れるキャラクターになります。引き出しの中身は1つのキャラクターにつき最低でも5個くらいは使った方がいいかなって思います。
と、簡単に言ってしまいましたが、この組み合わせで躓く役者がすごく多いと思うんですよね。
引き出しと引き出しの中身を増やすのも大変なんですけど、そこまでできた役者が次に足踏みするのが絶対ここだと思います。うまく組み合わせられるときもあるんですけど、意外と似たようなものの組み合わせが結構難しいんですよね。
どうしたら出来るようになるかって言われるとすごく答えにくいんですけど、何というか、引き出しの中身をきっちり整理するって感じですかね。
曖昧な区分けにしておくと、組み合わせた時に調整がきかなくなると思うんですよ。いつでもその引き出しの中身を完璧に取り出せるように身体と感性を鍛えておくしかないんじゃないかと。うん、やっぱり大事なのはそこですね。
その上で問21
問21「いわゆる「普通の女性」のミランダ役、めっちゃ難しかったと思うんですけど、気を付けたところを10個教えてください。」
引き出しと引き出しの中身を増やして、組み合わせも自由に出来るようになったらいよいよ最終段階。ボリュームの調整です。
ここでも照明に例えて話しますね。
舞台上にどの色をどれくらい当てるかというのは、全部ボリュームで決めています。例えば、このライトはボリューム2でこのライトはボリューム8、このライトは消しておいて、ここにこの色をボリューム5で当てる……みたいな感じです。
この作業をシーンによって、あるいはシーンの途中でもどんどん切り替えていくのがカラクリの舞台照明です。青い照明の中にも赤い色や緑色も入っていたりして、その比率もどんどん変わっていきます。気づくと赤色がメインの舞台に変わっていたり、いつの間にか昼間から夜の雰囲気に舞台が変わっていたりするわけです。
で、役者におけるボリュームの話。
役者のキャラクター作りも同じです。引き出しの中から引き出しの中身を選び組み合わせを決めたら、それぞれをどのくらいのボリュームで出すのかが次のステップになります。
役を演じる時は複数の引き出しの中身を組み合わせた方がいいって話をしましたよね。それぞれの引き出しの中身は、照明同様、シーンによってそのボリュームが変わるわけです。このボリュームがONかOFFしかないと細かい調整が出来ないんです。
ボリュームは細かく設定できる方が絶対いいです。携帯みたいに段階でボリュームが変わるものよりも、手動で細かい調整ができるものの方が自分好みの調整をしやすいのと一緒です。
「普通の女性」であるミランダを演じた時に1番気を付けたことがまさにこのボリュームなんです。
引き出しの中身も結構使いましたし、そのシーンにだけスパイス的な感じで使った引き出しの中身とかもありました。そしてそれを全部コントロールするためのボリューム調整が本当に細かかったことを覚えてます。このシーンでは引き出しの中身Aはボリューム3で、引き出しの中身Bはボリューム8、Cは1くらいで、Dを一回10にあげてそのあと6に落とそうかな、みたいな感じです。
「普通」であるということは、観客が気づいた時にはすでに変わっていたと印象を持たせることが大事です。ボリューム調整をしながら、少しずつ確実に変化させていくんです。決して劇的に変わるのではなく、いつの間にか変わってたんだけども何が変わったのかよく分からないくらいの微調整をしないといけない。
どの引き出しの中身をどのタイミングでどのくらいのボリュームにするのか。引き出しの中身を吟味して、時には中身を減らしたり加えたりしながら微調整をしていく。
どの役を演じる時にも同じなんですけどね、「普通である」という表現をするためにはいつも以上のボリューム調整が必要がでした。
なのできゅん。
今回の質問の答え、10個もありません。
問21「いわゆる「普通の女性」のミランダ役、めっちゃ難しかったと思うんですけど、気を付けたところを10個教えてください。」
解答 細かいボリューム調整 以上